
おそらく次のアカデミー賞で、故ヒース・レジャーの助演男優賞をはじめ各賞を総ナメするであろう「ダークナイト」版のバットマンのフィギュア。

おそらく次のアカデミー賞で、故ヒース・レジャーの助演男優賞をはじめ各賞を総ナメするであろう「ダークナイト」版のバットマンのフィギュア。
Magnetosphere revisited (audio by Tosca) from flight404 on Vimeo.
巷では古いネタかもしれないけど気に入ったのでメモ。
それにしてもきれいやわ~。
Weird Fishes: Arpeggi from flight404 on Vimeo.
これもいい。
次の新作は期待できるかもしれない。プロデュースがenoだし。しかしこのCMかっこいい。
| 美しき生命 【初回限定盤】 |
|
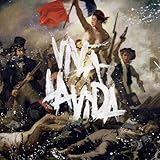 |
コールドプレイ
EMI MUSIC JAPAN(TO)(M) 2008-06-11 |
「やまけんの出張食い倒れ日記」で有名な山本謙治氏による日本の食卓に対する「安すぎません?」というこれまでなかったアプローチでの問題提起。
「安さ」を代償に見えないところで自分たちのカラダを蝕んでいっている悲しさを痛感する。
私は、この本の中で紹介されている「大地を守る会」を利用しているが、ここで買うことができる農薬にたよらない野菜、有機野菜や肉・卵・魚介類そして添加物を使わない加工食品を口にすることで、いっそう「安さを代償に失っているもの」の尊さを痛感してしまう。でもそれは、キレイ事ではなくて、単に「んまい!」という非常に簡単なことであって、美味い料理を口にする為にお金や時間や移動などの労力を費やすように、「安さを代償としない食材」を口にするために、市販品の食材を手にするよりもちょっとだけ(たいていほんの数10パーセントだけ)いつもより多くお金を払いたくなってくるのも事実である。
実際に、「安さを代償とした」食材からトマトのちょっとした酸味、ニンジンのなんとなく感じる化学薬品ぽさというか舌の中に残る抵抗、牛乳のなんとなく漂うあのクサ味・・・、そんなものが全部なく、とにかく味がやさしく抵抗のないトマト、野菜の具材だけで満足いくスープがつくれるニンジン・じゃがいも・玉ねぎ、歯ごたえや味に深みと逃避の姿勢が見られない畜産製品・・・、とにかく誉めだしたらキリがないほど美味く、口全体で味を噛みしめても決して嫌な気分になることのない食材を口にすると、とにかく「安さを代償にした」食材を買うことそして口にすることがバカらしくなってしまう。
これはとっても贅沢だなあ、と思う反面すべての有機農法は戦前ぐらいまでは100%そうだったんだなあ、と思うと(農薬にたよらない有機農法は自然との戦いで本当に大変なことだけど)、安さを代償に不必要に損をしていると感じてしまう。
なんだか本の紹介というより大地を守る会の紹介になってしまっているが、この本は必読だと思う気持ちは変わらない。
ずっとさがしもとめていたエコバックを発見。おりたたんだ状態になると3センチ程度になって非常にコンパクトに。オススメです。
京都でゲットした地元の雑誌「京都色濃い目マガジン 京都CF」。
さすが地元の雑誌だけあって、老舗から80年代、そして最近のカフェブームまで見事なまでに京都のカフェを押さえた一冊になっています。
「網羅性」という意味では類を見ないクォリティなので興味のある方は是非!
偶然見つけたクルーグマン教授による「ミクロ経済学」教科書。今の学生が本当にうらやましい、というか正直嫉妬心を覚える程。難解な事象を難解なまま相手にひけらかし悦に浸る、ということが全くもって「頭がいいこと」ではないことを教えてくれた氏の著作なだけにかなり期待。10年ぶりの復習になってちょうどいいや。2009年?に出ると言うマクロ経済学も要チェック。
会社と家との往復で読めてしまった。つまり1時間。
内容が薄いわけではなくて(まあ文字量は少ないですけど)、あまりに内容が整理され、使われている言葉が適切過ぎて、アタマにすらすらと入ってきてしまうから。
1時間の時間が空いたら色々なケースを思い浮かべながら3~4度は読み直したいと思った。
広告コピーを書く、というテーマだけじゃなくて、人に何かを伝える仕事に携わっているヒトならば誰でも共感できる内容が収まっているので、どんなヒトにでもおススメできます。
それにしても「企画書だけ先にうまくなっても意味がない」をはじめ、新人の頃当時の上司に言われた言葉が各所に散在していて、なんだかやたらと昔のことを思い出しました。
The Go! Team との出会いは変な形で、PS3の「Little Big Planet」のデモの音楽として出会った。このデモを見たときに、ゲームの画面ではなく「音楽がスゲー」と関心したものだ。
日本でもAXEのCMで使用されたり、ナイキのCMでも使用され
、音楽通の間ではひそかに支持者を増やしつつあるアーティストだ。
The Go! Team の魅力は、M.I.A. にも通じる21世紀の先端音楽がもつ、あらゆる音楽の混成からなるハイブリット感とそのオリジナル性だろう。そこで奏でられる音楽は先端でありつつもどこかでノスタルジー色が強い。「Get It Together」なんかで聞く事ができる、なんとなく日本人的なメロディーを感じるのもいい。だからといって単にやさしいだけではなく、一方でドラムに代表されるリズム感は時に暴力的だったりする。
最近音楽に閉塞感を感じていただけに、こういうアーティストの登場は本当にうれしい。
ふだんはスローペースで本を読むというか、部屋中積本状態で本を買っただけで読んだ気になっている私ですが、私の中では今月は結構数を読んだので記念にリストアップ。しかもどれもおもしろかったし。
今回読んだ本は、結果的に「国策捜査」というテーマを意識して読んでいて、「国策捜査」と言う言葉は、「検察庁・国家の陰謀」といった安易なイメージで語られることが多いけど、実際は佐藤優氏の「国家の罪」で描かれているように、政局や社会のパラダイム転換が生じた際に、変化を象徴的に社会に伝える為に、検察が法解釈の基準をちょっとだけかえて(まるでサッカーの審判のジャッジが変わるように)、一部の人間を犯罪者というかアイコン化すること、というのがよくわかった。
元東京地検特捜部出身のヤメ検弁護士田中森一氏の自叙伝。必要悪を認めず清廉潔白で幼稚な世論こそ真実だと思い込んじゃっている人以外にはオススメの本。この本を出版した幻冬舎の見城さんがやっぱりすごい、と思った。


 正直疲れました
正直疲れました 自分の人生を考える時にお薦めです
自分の人生を考える時にお薦めです 国家権力の毒
国家権力の毒 元特捜検事が描く、バブル経済、裏経済と表経済の交錯、国家権力中枢
元特捜検事が描く、バブル経済、裏経済と表経済の交錯、国家権力中枢 戦後日本の光と影が描かれています
戦後日本の光と影が描かれていますby G-Tools , 2007/09/01
「反転」の田中森一氏の事件を外側にあたる魚住昭氏の視点から描いた作品。田中森一氏の著書を通しての発言がどの程度公正なものであるのかを検証するために購入。


 三つ子の魂、百まで
三つ子の魂、百まで 正義はなにか?
正義はなにか? 自己主張する検察
自己主張する検察 慄然とする
慄然とする いろいろ考えさせられます。
いろいろ考えさせられます。by G-Tools , 2007/09/01
まず読むべし。「外務省のラスプーチン」と呼び彼を犯罪者とみなすことがどれだけ滑稽なことであったのかを思い知らされる一冊。西村検察官とのやり取りは本当に秀逸。「実質識字率5%」、「週刊誌の中吊りとワイドショーで実質的に世論は形成される」という言葉は耳が痛い。あと、鈴木宗男さんすみません。田中森一氏にちょとだけ触れる箇所があって、そこで鳥肌。


 政治の裏側が垣間見えました。
政治の裏側が垣間見えました。 この本から学ぶことは多い。
この本から学ぶことは多い。 読むべし
読むべし 「日本人実質識字率5パーセント」を少しでも上げる意味でも読んでみたい
「日本人実質識字率5パーセント」を少しでも上げる意味でも読んでみたい 国家に関わる人間たちの異常性
国家に関わる人間たちの異常性by G-Tools , 2007/09/01
「国家の罠」を受けて、佐藤優氏の著作を読むという目的で購入。第38回大宅ノンフィクション賞受賞、第5回新潮ドキュメント賞受賞の社会的にも評価を受けた作品。「国家の罠」もそうだが、佐藤氏が過去の出来事を刻銘に記憶していることに、本当に氏の能力の高さを痛感する。ラストの「国家の罠」へのつながりが秀逸。


 ソ連の崩壊に巻き込まれながら過ごした青春の物語
ソ連の崩壊に巻き込まれながら過ごした青春の物語 「外務省のラスプーチン」が誕生するまで
「外務省のラスプーチン」が誕生するまで プロフェッショナルとはを考えさせられる
プロフェッショナルとはを考えさせられる 人と交わること
人と交わること 素晴らしい本だが、警戒しながら読んでほしい
素晴らしい本だが、警戒しながら読んでほしいby G-Tools , 2007/09/01
佐藤氏と9.11のアナウンサー元NHKの手嶋氏の対談集。互いに褒めあう姿が気持ち悪いが、軽い気持ちで読めていい。佐藤氏に対するバイアスが残っている人は「国家の罪」を呼んでから手を取った方がよいと思うので入門書には勧められない。


 対談は悪くありませんでしたが……
対談は悪くありませんでしたが…… 丁々発止
丁々発止 褒めあい
褒めあい 国際諜報小説を読みふけるような面白さだが、現実世界の出来事となると、、、。
国際諜報小説を読みふけるような面白さだが、現実世界の出来事となると、、、。 ■日本の外交の二人の巨塔による傑作!
■日本の外交の二人の巨塔による傑作!by G-Tools , 2007/09/01